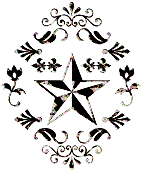※ヒロインさんのいとことして登場する菊音=「アルバイト、はじめました」のヒロインとなります。 背景など詳細を知りたい方はぜひこちらの作品をご一読をお勧めいたします。
「ちゃん、どうだった?」 研修室を出ると、従姉妹の菊音ちゃんが待っていてくれた。 「う、うん。挨拶の練習とか、丁寧語の使い方とか、そういうマニュアルあるんだろうなって思ってはいたけど、お辞儀にも規定があるなんて知らなかった」 私はトヨトミルド接客マニュアルという分厚い冊子を抱えて、菊音ちゃんと並んで歩きだした。 ここは、トヨトミルド・バーガー社があるビル。そこの一角にある研修ルームに今まで私はいた。 トヨトミルドに勤める人は、実際に現場に出る前に、色々な研修を受ける。アルバイトは実店舗で、正社員や契約社員は、今の私みたいに本社の研修施設で、一堂に会して受ける場合もありで、採用時期などでそれらは臨機応変に行われる。 「あ〜 お辞儀ね。そうそう、細かいところまで決められてるからね」 菊音ちゃんは、私の母方の従姉妹だ。菊音ちゃんのお母さんと私のお母さんが姉妹。年が近いので、幼い頃から互いに行き来していた。そして今でも仲良しだ。 「ねえねえ、噂に聞いたんだけどさ」 私は声を低めて、菊音ちゃんに囁いた。なになに? と菊音ちゃんが顔を近づける。 「石田さんのお辞儀の研修でさ、分度器で計ってダメだったら物差しでひっぱたかれるって、ホント?」 私の真剣な顔を見て、菊音ちゃんがプッと吹き出した。だって、噂の石田さんだったらやりかねないなぁって思ったんだもの。 「やだぁ〜 ちゃんてば。あの人、確かに仕事態度厳しいし、言い方も一見冷たいけど」 菊音ちゃんは頬を染めた。 「心根はいい人よ」 はーいはいはい、ごちそうさま! そう、鬼の指導員と言われるトヨトミルドの名物?社員石田さんは、菊音ちゃんの彼氏でもある。まだ直に会ったことはなくて、遠目でしか見たことないんだけどね。 菊音ちゃんの様子を見て、私は微笑ましくも羨ましくも思った。菊音ちゃんのお母さんで私の叔母でもある「ねね」さんは、早くに亡くなり、菊音ちゃんはお父さんに育てられた。といっても、ファーストフード業界の覇王と言われる秀吉叔父さんは多忙を極め、菊音ちゃんは家政婦さんやベビーシッター、そして有能な秘書に世話を焼かれて大きくなった。いっときは、父親である秀吉社長を憎んでいたことも、私は知っている。 うち(ねねの実家)は、本当にごく普通のサラリーマン家庭で、幼児の菊音ちゃんはよく預けられていた。昔は頻繁に行き来していたのだけれど、破竹の勢いのトヨトミルドは経済新聞を賑わすような大企業に成長すると、それに反して、私たち親戚の付き合い方も変わってくる。 入ってくるお金、住むところ、暮らし方。格差が広がると、どうしても付き合いづらくなる。 うちの父は、秀吉叔父さんを尊敬もしたし、劣等感にも苦しめられた。 叔父さんは叔父さんで、勤め人は覇気がないと感じてしまうらしい。また稼ぎをあてにする輩も近づいて閉口することもあったようだ。 そんな大人たちの思惑を余所に、従姉妹同士は仲良くやっていたけれどね。 私こと は、某大学の経済学部に在籍している。卒論のテーマはファーストフード業界の動向とこれからの課題。これを引っ提げて、大学院へすすみ、経済論をうちたてて、目指せ華の経済アナリスト!と、ぶちあげたのはいいけれど、まだその論文のための資料も集められないヒヨッコなのだ。 秀吉叔父さんは、努力する人は好きらしい。私の論文を書く悪戦苦闘ぶりを知って、ならば現場を体験するがよかろうと、半年間の契約社員という経験を許可してくれた。 といっても、豊臣の親戚というのは勿論伏せて。研修も仕事も、給与も、一般と同じ条件だ。手加減は一切なし。 『うちの店に損失出したら、例え秀吉の姪でも許さないからね』 と、微笑んだ、叔父様の右腕の竹中さん。目は全然笑ってなかったわよ! で、私は今日、他の皆さんと同じくトヨトミルドの先兵(これ、石田さん受け売りらしく菊音ちゃんが教えてくれた)となるべく研修を受けたわけだ。門外不出のマニュアルも読めるし、接客のノウハウも学べる貴重な体験だけど、思ったよりも覚えること身につけること山積みで、私は大丈夫かなぁって不安。 『大丈夫よ』 なんて菊音ちゃんは言ってくれるんだけどね。
何だかんだで社員経験一ヶ月目。私はオフィス街の一角にある、売り上げTOPの店に配属された。菊音ちゃんと同じ職場では緊張感ないからと、あえて違う店だ。まあ、それはいいんだけどね。通り向こう違うだけだし。 まあ、とにかく忙しい一ヶ月。大きな声で挨拶するだけで手いっぱい。口を動かしながら手を動かす。お客様の目つき、様子で瞬時に他のメニューを勧めるなんて芸当はまだまだ出来ない。言われたことをやるだけでフラフラの毎日を送っている。 学校で講義を受ける、図書館に通う生活になれた身では、一日立ちっぱなしというのも疲れるもので。 休日に菊音ちゃんの店に偵察に行ったら、彼女は慣れた様子でバシバシ仕事をこなしていたので、自分は劣等感にさいなまされたものだった。菊音ちゃんは、『ファイト〜』なんて励ましてくれて、大谷さんというベテラン社員さんは、偵察のつもりで見つかった私のあたふたした様子に『ヒヒヒ』などと笑いながら、シェイクをご馳走してくれた。 今日は遅番で。つまり今は深夜。疲れた足を引きずりながらも、仕事仲間に挨拶をして店を出る。 このまま下宿先に戻って、カップめんを作る気力もないぐらい、今日は本当に疲れていた。お腹は減っている。でも、バーガーを食べる気は起きなかった。パテの焼ける匂い、揚げ油の匂いは、十分に堪能しました。何か全然違うものを食べよう……。 というわけで、私は深夜の道をトボトボ歩きながら、ヤスバーガーを素通りし、ダテッシュネスを通り過ぎ、マツナガックスカフェに入った。 ここはちょっと高級感のあるインテリアが売りの、おしゃれな人に人気の店だ。その分、コーヒー一杯のお値段も、トヨトミルドの3倍なわけだが、安らげる場所を提供してくれている。 ダンディなおじさま(店長らしい)とジャズの調べ、コーヒーのこうばしい香りは、せわしない一日を過ごしたこの身を、ゆったりした気持ちにさせてくれた。 私は野菜たっぷりのキッシュをレンジで温めてもらい、ローファットミルクたっぷりのカフェラテを飲んでくつろいだ。 店長さんに 「もっと己の欲のままに過ごしてはどうかね」 などと言われたが、深夜にそんな美味しそうなロールケーキを見せてくれるな!と、誘惑を何とかはねのけた。 さて、お腹もふくれたし、帰ろうかな?と、バッグをのぞいて、私は慌てる。ケータイ、店のロッカーに置いてきちゃった。 どうしようかなと迷ったけれど、明日は午前中講義で、バイトは遅番。それまで電話がなかったらやっぱり困るので、私は来た道を引き返した。 さすがに店は真っ暗。そりゃそうよね。私は合い鍵を使って、従業員用のドアを開けた。 えーと、スイッチはどこだっけ?v 足を踏み込み、スイッチを手探りしていると…… ぼふっ 思い切り、温かくて固いものにぶつかる。こんなところに壁……じゃない。物……じゃない。この感触は生き物? 真っ暗な中、その何かの息づかいと圧迫感と肉の感触が間近に迫って…… 「ぎゃあぁぁぁーっ 熊ーっ!?」 私は悲鳴をあげながら後ずさった。 「おいおい、何でこんな所で熊なんだ。泥棒と言われるより、小生は傷ついたぞ」 熊……じゃない、その生き物は低い声で悲しそうに言い返してきた。 「あ、そっか。ど、ど、泥棒ーっ!?」 だって暗い中でゴソゴソしているっていったら……。私はまた悲鳴をあげそうになった。 「あー、待て待て。小生は泥棒ではないんだって!」 その低い声は、慌てて私を宥めだした。ええい、埒があかない。私は腕をのばして、スイッチを探り当て、灯りをともした。 パチッ 急に周囲が明るくなり、私は眩しさに目をつぶったが、恐る恐る目を開ける。目の前には大柄な男性が立っていた。 本当に大きい人。私が熊と叫んだのもわかってもらえると思う。縦も横も大きくて。あ、でも決して太っているという感じではない。筋骨隆々という感じだ。私みたいな小娘を捻りつぶすなんて造作もないだろう。 前髪を長く垂らし、表情は一切見えない。 でも、何故だろう? こんな間近で接しているのに、威圧感というか攻撃的な感じが全然しなくて、戸惑いながらも面白がっているような雰囲気がする。 あ、口元が笑みで歪んでる? 「やれやれ、まいったな。そっちこそ、不意に入ってきたんだから、泥棒かもしれないじゃないか」 皮肉っぽい笑みを浮かべたその人は言った。私を髪の間から見ている。 「そんなっ。私はここの契約社員です。ほら、合い鍵!」 私は合い鍵を見せた。それからトートバッグからトヨトミルドのIDカードも出して見せた。 「ふーん。小生も持っているぞ」 男は作業着の胸ポケットからトヨトミルドのIDカード(社員証)を取り出す。私は顔をぐいっと近づけて、そのカードを眺めた。 「最果て支局 材料調達部 黒田……」 「『かんべえ』だ」 どうやら本当にトヨトミルドの社員さんらしい。でも、最果て支局ってどこ? 「黒田官兵衛さん、最果て支局ってどこですか?」 思わず聞いてしまった。黒田と名乗った男は恨みがましく自分の社員証を見直した。 「小生も知らん。エビの調達に、地球の裏側に行っている間に、勝手にこんな肩書きつけられた……。くそっ 大方、刑部の嫌がらせだろう」 派閥抗争でもあったのかなー? だって最果てって…… 「あー、待て待て。島流しとか、左遷されたとか思うなよ。これでも、小生、トヨトミルド若手社員の出世頭、豊臣の両兵衛と名高いんだぞ」 本当かな? 私はすぐに顔に出るたちなので、黒田さんはアレコレ言い出した。 「お前さん、この春出たプリプリエビバーガー知っとるか? あれは小生が調達したエビなんだぞ」 「えー、本当ですか。あれ、すごい人気商品なんですよ」 それは本当だ。濃厚で甘みの強いエビを使ったバーガーはいつも売り切れるのだ。 黒田さんは、えっへんとふんぞり返った。 「そうだろう〜。あのエビは、南の海の深海でとれるなかなか珍しいヤツでな。あれを一定量確保するのに、どれだけ苦労したことか。現地に行ったきりになって、戻ってきたら、何故かこんな肩書きになってた……」 この人スゴいんだか、弱いんだか、よく分からない人だな。何だか落ち込ませてしまったようで、私は話を変えることにした。 「えーと、黒田さんは、何で今、ここにいらしてんですか?」 「ああ、新作バーガーの試作にな、新しい材料を持ってきたんだ」 床に転がるクーラーボックスを、黒田さんは拾い上げた。私がぶつかった時に落としてしまったらしい。 「この中に、新作バーガーのメインが入っている。今日はここの厨房で試作をすることにしているんだ」 「そうだったんですね」 と、相づちをうつと、店に続くドアがガシャンと開けられた。 「おい、黒田! いつまで待たせる気だ。秀吉様のためのバーガーの件はどうなっている!」 怒鳴り込んできた特徴的な前髪の男性……石田さんだっ! 「暗〈くら〉よ。何を手間取っておる。フヒヒ…… 実は、持ってくるのを忘れたとか、中身が腐っておるとかではなかろうな?」 後に続く細身の男性は、この前会った、大谷さんだった。 「何ーっ! 貴様、秀吉様に腹切ってお詫びしろーっ!」 石田さんの声に、黒田さんはウヘッと首を竦めた。 「いや、忘れてもないし、傷んでもない。ちょっと立ち話をしていただけだ」 大谷さんが、オヤ?というようにこちらを見た。私は慌てて会釈をした。 「すぐに取りかかれ! 時間が惜しい」 石田さんと大谷さんがすぐに厨房へ向かった。黒田さんがクーラーボックスを抱えて、それに続く。ふと振り返った。 「お前さんも食べてみるかい?」 あの二人に囲まれてやいのやいの言われる黒田さんはすぐに想像できた。彼自身、ちょっと気が重たくて、私に声をかけたのかも。私は黒田さんをそのままほっとけない気持ちと、好奇心にかられて頷いた。 厨房ではフライヤー(揚げ物鍋)はもう温まっている。黒田さんは、クーラーボックスを開けて中の魚を取り出した。 「…………」 思わず全員後ずさる。だって、その魚、黒くて目がギョロリとして、体はブヨブヨで、お世辞にも美味しそうに見えなかったのだ。 「これは、あのエビバーガーがとれる深海にいるタラの一種でな。見かけはグロいが、エビをたっぷり食べたこの身は、甘みがあってうまいんだ」 黒田さんはそう言いながら、魚をさばく。その手際は見事だった。 でも、この人、間が悪いというか運が悪いというか、フライヤーの油が跳ねて火傷しちゃうし、棚を開ければ調理器具が頭に落ちてくるしで、何だかドタバタだ。 それでも何とか魚のフライはできて、三枚の皿に盛りつけられた。 「いただきます」 私たちはそれぞれ、プラスチックフォークをそのフライに突き立て、頬張った。 シャオッ 衣が気持ちいい音をたて、湯気がほわんとたつ。黒田さんの言うとおり、魚は身離れがよくて、肉の甘みが強く、美味しかった。 「美味しい〜」 私は思わずという感じで、気づいたら声に出していた。 「だろう!! だろ、だろー?」 黒田さんが嬉しげに言う。黙って咀嚼していた石田さんが、フォークを置いた。 「それで、ソースは? 付け合わせの野菜は?」 続いて大谷さんが、黒田さんに向き直る。 「食材の良さは分かった。だが、これは完成品ではないぞ。バーガーとしての形をとらねば」 「…………」 黒田さんがアタフタしはじめる。 「いや、その、考えはあるんだ。子供用と大人用の二種類のソースとか……」 「ソースは?」 二人が異口同音に聞いた。嬉しげだった黒田さんの肩がすぼまる。 「完成していないのを秀吉様にお見せできないぞ」 「やれ。バンズ、ソース、野菜を決めてから、試作品と名乗りゃれ」 石田さんと大谷さんが見事な連係プレーで、黒田さんを凹ました。 「だが、メインは決まった。ということで、この夏はフィッシュバーガーじゃな」 大谷さんが言うと、石田さんが頷いた。 「我々もソースの試作とりかかるか。おい、黒田。この魚をもらっていくぞ。いつでも必要量送れるようにしておけ」 「フヒヒ。余りトロトロしておると、我らが完成させてしまうかもしれぬぞ?」 黒田さんへの愛のムチ? を残して二人は、クーラーボックスを抱えて立ち去った。 私と黒田さんが取り残される。 「…………」 私は皿に残ったフライをまた口に運んだ。 「あ、あのっ 本当に美味しいです。マジウマですよ」 元気づけたくて言ったら、黒田さんがすぐその言葉に飛びついた。 「そうだろ! そうだろっ! 小生には見る目あるだろっ!」 前向きつーか、立ち直り早いな、この人。にかっと笑った時に見えた白い歯が眩しかった。笑いながら前髪をかきあげると、涼しげな目が現れて、私はちょっとドギマギしてしまったのはナイショ。 「よ、よしっ。ソースと野菜が決まれば、手柄は全部、小生のもの。見事、経営陣返り咲きだ〜」 未来への展望が開けたらしく、ぱあぁっと明るくなった黒田さんは鼻歌をうたいながら後かたづけを始めた。私は忘れ物を取りに来たことを思い出して、ロッカーへ向かった。 用事を済ませて厨房をのぞくと、黒田さんは帰り支度をしていた。明日から、ソース作りに向けて頑張るらしい。私も一緒に店を出ることにして、後に続いた。 「なあ、お前さん」 鍵をしめた時、黒田さんが話しかけてきた。 「ソース作ったらな、また、食べてみてくれないか?」 「え? いいんですか?」 非常口のランプの下、二人は向き合う形になった。 「お前さんが美味しそうに食べていたのを見てな、何というか、この会社に入ったときの自分を思いだしたんだ」 黒田さんは言った。 「ずっと働き続けていくうちに、小生は出世することばかり考えていた。だがな、元々は、人に美味しい物を提供したいという気持ちが原点だった。そのためにこの仕事を選んだんじゃないかって、今更ながら自覚したんだ」 ああ、それは素敵な考えだ。私は素直にそう思ったものだから、「ハイ」と頷いた。 「ところで、ソースの当てはあるんですか?」 「うーむ…… 白身魚は淡泊だからなぁ」 黒田さんはまた背を丸め、ぼりぼり頭を掻いた。 「現地ではどんな風に食べてるんです?」 「油で揚げて、ライムやレモン搾ってるなぁ。あー、青唐辛子刻んだの添えたりしてたっけ」 「レモンソースとかさっぱりしていいじゃないんですか?」 軽い気持ちで言ったら、黒田さんが急に身を起こした。 「レモンソース! そうか! それはいいかもしれない!」 手帳を取り出し、非常灯と街灯の光の元で、何かを書き付ける。 「唐辛子系もあうんなら、サルサ……とか?」 重ねて言うと、「いいぞ〜 いいぞ〜」と小躍りして、またメモをとっていた。 「あ、でも、私だったらエビチリみたいな甘辛いのがいいなぁ」 呟いたら、黒田さんが、私を振り返った。 「チリソース! それもいいな。待てよ、エビバーガーをいっそエビチリにしてもいけるんじゃないか? エビバーガー第二弾なんてどうだ」 「あ、それも美味しそうですね」 私が言うと、黒田さんは、刑部らに目に物見せてくれぬと言って笑った。明日からすることがいっぱいできて嬉しそうだった。 「お前さんは、小生にとって、アイデアの女神さまだな!」 女神と言われてイヤな女はいないだろう。例え、それがソースの味に関してだけだとしても。 私は照れ笑いを浮かべた。
「ふーん フィッシュバーガーね」 トヨトミルド副社長の竹中半兵衛は皿の中のフライを見た。 本社に戻ってきた石田と大谷が、まずはということで、魚をフライにし、トヨトミルド人気のフライドポテトと一緒に皿に盛りつけ、フイッシュ&チップスの体裁にして竹中に見せていた。 塩だけで味付けたフライを食べた竹中は、「へえ、美味しいじゃない」と呟いた。 「ですが、黒田はメインだけで、味付けも野菜も決めていません。これでは、秀吉様に試食させられぬ未完成品です!」 石田が憮然と言う。大谷がヤレヤレと笑った。 「まあ、明日から暗(くら)の奮闘ぶりが楽しみよな」 二人にとっちめられた黒田の様子が目に浮かび、竹中はフフフと笑った。決して黒田を侮っているのではない。それどころか、彼はこの会社きっての凄腕だと思っている。そしてその手腕がいかんなく発揮できるのは、困難な目にあってこそだと、竹中は感じていた。だからこそ、石田と大谷を煽って黒田を追い込んでもいるのだ。 「まあ、若手の女の子に旨いと言われ、喜びはしゃいでおったから、あれはあれで、今頃は覇気が戻っておろうな」 大谷が、居合わせた契約社員のことを思い出して、ついでに竹中に様子を話した。竹中が、「ああ」と頷く。 「……ちゃんだっけ」 「菊音殿と親しそうにしていたのを見たことがありますな」 「菊音と……?」 「やれ、三成。気がついておらぬのか? あのおなごは、菊音殿の従姉妹よ」 「そうなのか」 などと三人が話していると、奥で業務報告書を読みふけっていた豊臣秀吉が、顔をあげた。 「ああ、それは我の姪のことだったのか」 「そうだよ」 竹中が肯定する。 トヨトミルドの頂点である、秀吉社長は報告書を置いて、昔を懐かしむような顔をした。 「うむ。あれはオナゴだが、なかなか気骨ある。鍛えがいありそうだ。本人が望めば、このまま勤めればよい」 珍しく秀吉社長の口調は柔らかかった。何だかんだで、娘や姪を彼なりに愛おしんでいるのだろう。 「へぇ〜」 それは大したことない雑談であったが、半兵衛は何となしに呟いた。 「ふぅん。それも面白いかも」 黒田官兵衛という男は、困難に遭えば遭うほど実力が増すタイプである。だが、余りに道のり険しいと、彼は何か良からぬことを企てるかもしれぬ。そんな時は、褒美をちらつかせるのも、いい策かもしれない。そして、その褒美が、豊臣に繋がる者だとしたら……? 彼の忠誠はいやがうえにも増すだろう。 「ふふっ。なかなかいいかもね」 竹中は独りごちた。 勿論、トヨトミルドきっての策士の目に留まったなどと、この時のは知るよしもない。 ←back |